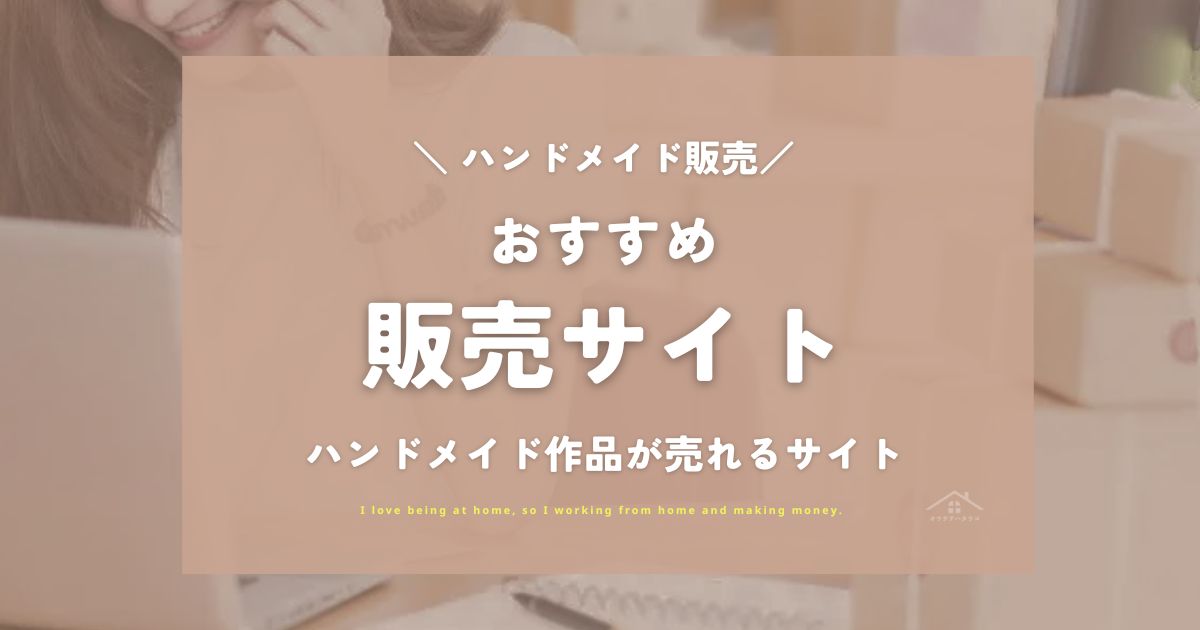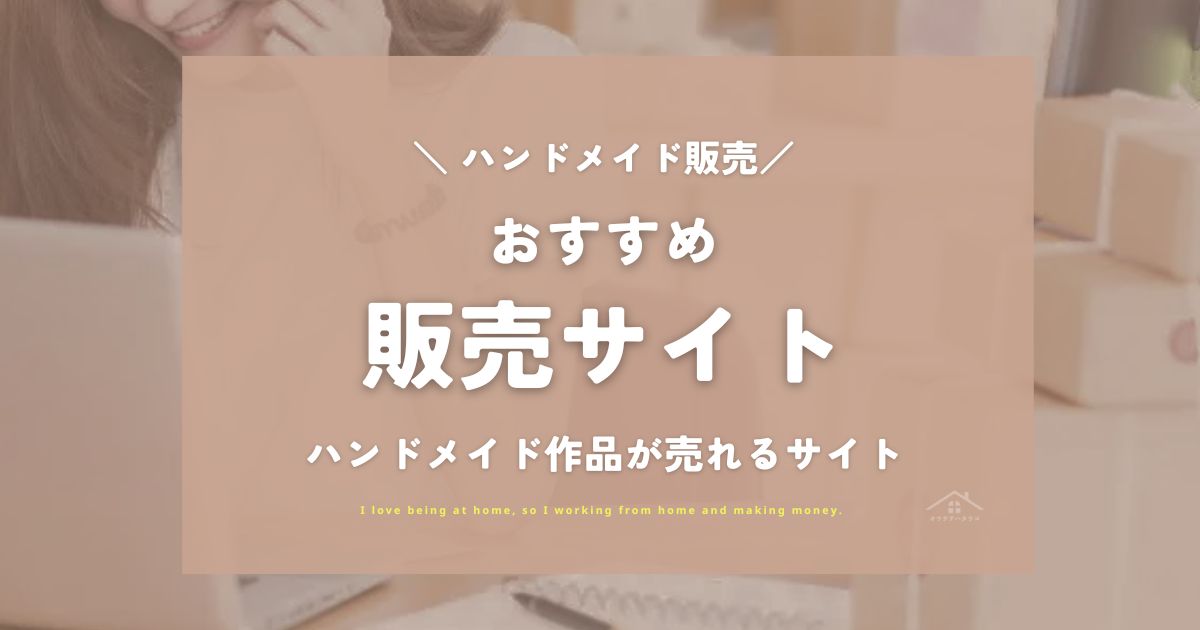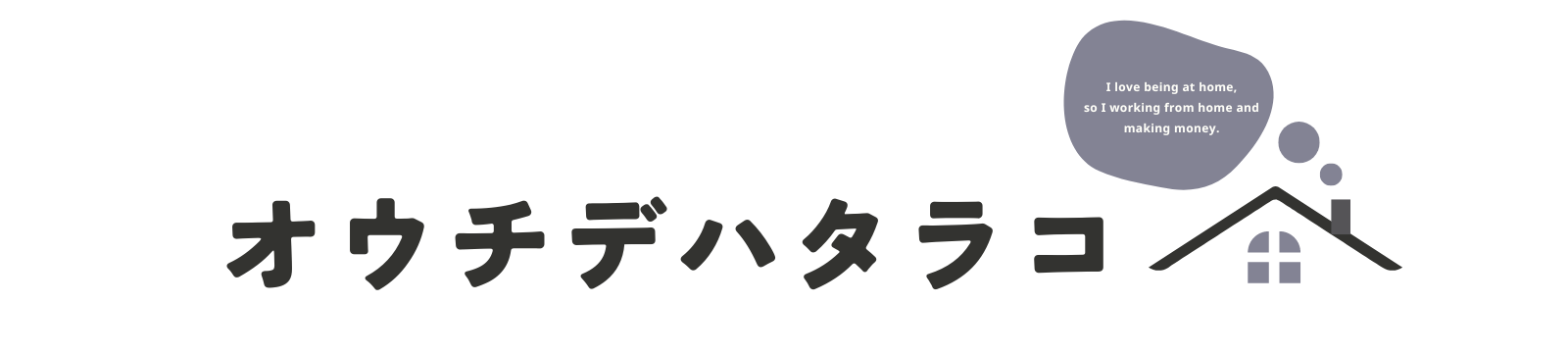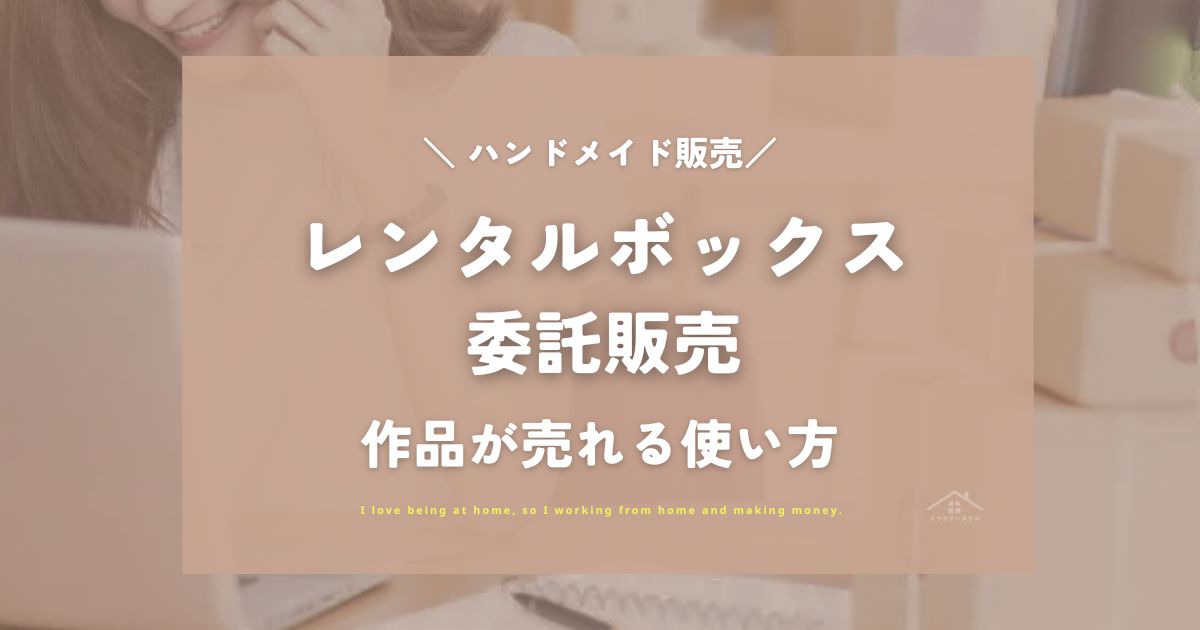ハンドメイド作品を作ったけれど、レンタルボックスや委託販売で本当に売れるのかな?
自分の作品をどこで販売すればよいのか、迷いますよね。
本記事では、レンタルボックスと委託販売の違いや売れるコツをわかりやすく解説します。
さらに、ネット販売との併用で販売の幅を広げる方法もご紹介。
この記事を読むことで、どの販売方法が自分に合っているのかがわかり、作品をもっと多くの人に届けられるようになります。
ハンドメイド販売で成功したい方は、ぜひ最後までご覧ください!


レンタルボックスと委託販売とは?
ハンドメイド作品を販売する方法として、レンタルボックスと委託販売があります。
それぞれの特徴について、詳しく説明していきましょう。
レンタルボックスとは?
個人のハンドメイド作家が手軽に作品を置けるため、実店舗を持たずに販売ができます。
レンタルボックスの特徴
- スペースを借りるだけで販売可能
- 自分で店を開く必要がない
- 対面販売なし
- 接客が苦手でも気軽に出店できる
- 売上は手数料を引かれた分を受け取る
- 店舗ごとに手数料率が異なる
例えば、商業施設の一角やハンドメイド専門店の中にレンタルボックスがあり、作家ごとに作品が陳列されています。
作品を購入したお客様はレジで支払いをし、売れた分の代金が作家に渡される仕組みです。
委託販売とは?
レンタルボックスとの違いは、売り場の管理やレイアウトを店舗側が決めることが多い点です。
委託販売の特徴
- お店側が販売を担当する
- 自分でお客様対応をしなくてよい
- 売れるかどうかは店舗次第
- 人気店なら売れやすくなる
- 販売手数料がかかる
- お店ごとに設定が異なる
例えば、雑貨屋やカフェの一角にハンドメイド作品が並んでいることがあります。
お店の雰囲気に合う作品を扱うため、作家のテイストと店舗の相性が重要です。
レンタルボックスと委託販売の違いとは?
レンタルボックスと委託販売は似ていますが、販売方法や手数料の仕組みが異なります。
| レンタルボックス | 委託販売 | |
|---|---|---|
| 出店方法 | スペースを借りる | お店に預ける |
| 販売管理 | 自分でレイアウトを決める | 店舗側が管理 |
| 手数料の違い | ボックス代が必要 | 売上の一部を店舗に支払う |
| 販売の自由度 | 自由にディスプレイできる | お店の方針に従う |
レンタルボックスは自由度が高く、自分のブランドをアピールしやすいです。
一方で、委託販売はお店の力を借りられるため、販売がスムーズに進む可能性があります。
どちらが向いているかは、作家の販売スタイルや商品ジャンルによります。
委託料はいくらかかるの?
ハンドメイドの委託販売手数料は、出店する場所によって大きく異なります。
一般的なレンタルボックスや小売店舗では20%~30%が相場ですが、百貨店などの大型商業施設では30%~50%になることが多いです。
また、販売手数料以外にも出店料や月額料金がかかることが一般的です。これらの料金は、商品を置くスペースの広さ によって変動します。
委託販売の費用について
- 小売店舗・レンタルボックスの手数料:20%~30%
- 百貨店や大型商業施設の手数料:30%~50%
- 出店料・月額料金が必要な場合が多い
- スペースの広さに応じて費用が変わる
ネット販売の手数料は10%前後のため、これと比べると委託販売の手数料は高く感じるかもしれません。
しかし、これらの費用には、以下のような販売サポートが含まれています。
委託販売の手数料に含まれるもの
- 展示スペースの提供
- 販売環境の整備
- 広告・宣伝のサポート
販売コストを抑えたいなら、ネット販売もおすすめ
販売コストをできるだけ抑えたいなら、ネット販売をおすすめします。
ハンドメイド作品のおすすめ販売サイトについては、下記の記事でくわしく説明していますので参考にしてください。
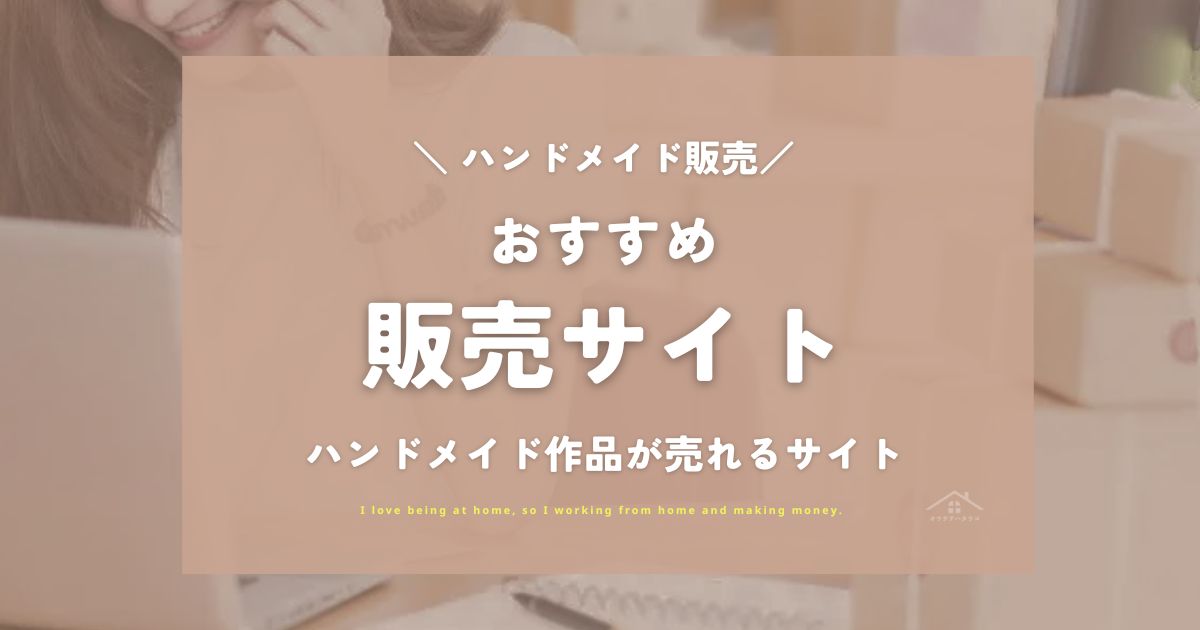
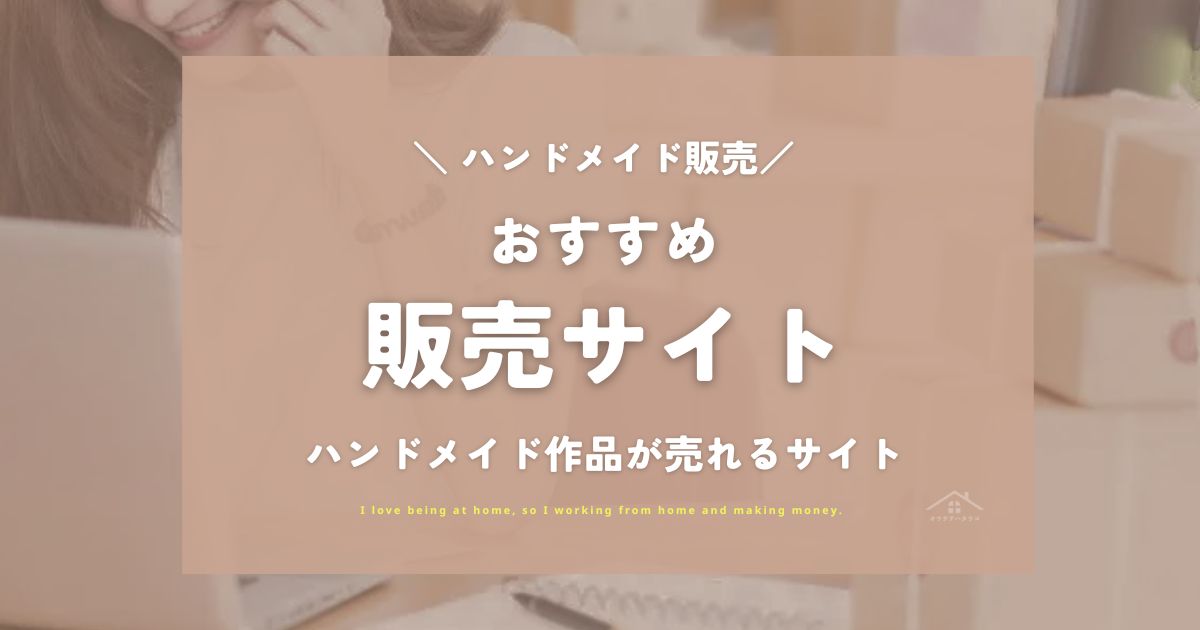
レンタルボックスや委託販売でハンドメイド作品が売れるコツ
レンタルボックスや委託販売を使って、ハンドメイド作品が売れるコツを見ていきましょう。
ディスプレイを工夫
レンタルボックスでは、ディスプレイが売上を左右します。
お客様の目を引く工夫をすると、手に取ってもらいやすくなります。
目立つディスプレイのコツ
- 高さを出す
- 台や棚を使い、立体感を作る
- 商品説明をつける
- 「手作り」「一点物」など特徴を伝える
- カラーテーマを統一
- ごちゃごちゃせず、スッキリ見せる
例えば、小物を並べるときは、単に置くだけではなく、高低差をつけると見栄えが良くなります。
また、「ギフトにおすすめ!」などのポップを添えると、お客様にとって魅力的に映るでしょう。
お店選びがカギ!相性のいい店舗の見つけ方
委託販売を成功させるには、お店選びが重要です。
相性の良いお店を選ぶことで、売れる可能性がぐんと高まります。
お店選びのポイント
- お店の客層と作品が合っているか
- 他の作家の商品が売れているか
- 店員さんが親切で、相談しやすいか
例えば、大人向けの雑貨店に子ども向けの作品を置いても売れにくいです。
リサーチをしっかり行い、販売チャンスを広げましょう。
レンタルボックスと委託販売は、それぞれメリットやポイントがあります。
売れるポイント
- レンタルボックスはディスプレイと価格設定が重要
- 委託販売はお店選びと作品の相性がカギ
- どちらもリサーチと工夫で売上が変わる
どちらの方法も、自分の作品を知ってもらうチャンスです。
まずは試してみて、販売のコツをつかんでいきましょう!
ハンドメイドを売るときの注意点
ハンドメイドを売るときの注意点は、下記の記事でくわしく解説しています。


ハンドメイド作品の委託販売先を見つける方法
ハンドメイド作品を委託販売するには、 SNSや検索サイトを活用する方法や、 店舗からスカウトを受ける方法があります。
自分から積極的に探すことで、委託先が見つかりやすくなります。
SNSや検索サイトで募集を見つける
TwitterやInstagramなどのSNS、または検索サイトを活用すると、委託販売を募集しているお店を見つけやすくなります。
検索のポイント
- 「レンタルボックス、ハンドメイド」
- 「委託販売、ハンドメイド」
- 「ハンドメイド作家募集」など
これらのキーワードで検索すると、ハンドメイド作品を扱う店舗の情報が出てきます。
募集がかかっていなくても枠が空いていることもあるため、気になるお店があれば直接問い合わせてみると良いですよ。
SNSやブログでスカウトを受ける
自分の作品をSNSやブログで発信していると、委託店舗から直接声がかかることがあります。
特に新しくオープンする店舗 は、委託作家を探していることが多いため、スカウトを受けるチャンスが高まります。
スカウトを受けやすくするコツ
- 作品写真を定期的に投稿する
- 「#ハンドメイド作家」などのハッシュタグを活用する
- プロフィールに「委託販売募集中」と記載する
チャンスを逃さないよう、常にSNSを活用して作品を発信しておくことが大切です。
レンタルボックス・委託販売のメリットとデメリット
ハンドメイド作品を販売する方法として、レンタルボックスや委託販売を利用する人が増えています。
しかし、それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分のスタイルに合った方法を選ぶことが大切です。
ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説します。
レンタルボックスのメリット
レンタルボックスは、決められたスペースを借りて、自分の作品を自由に展示・販売できる仕組みです。
レンタルボックスのメリット
- 自分のペースで販売できる
- 作品の配置や価格を自分で決められるため、自由度が高いです。
- 店舗にいる必要がない
- 販売はお店側が行うため、自分が店頭に立つ必要がありません。
- 商品をアピールしやすい
- ディスプレイを工夫すれば、自分のブランドイメージをしっかり伝えられます。
- 固定ファンを増やせる可能性がある
- 定期的にボックスを訪れるお客様がつけば、リピーターを獲得できます。
レンタルボックスのデメリット
一方で、レンタルボックスには以下のような注意点もあります。
- ボックス代がかかる
- 月額料金が発生するため、売れない場合は赤字になる可能性があります。
- 売れるかどうかは場所次第
- 人通りの少ない店舗では、作品を見てもらう機会が減ります。
- ディスプレイの工夫が必要
- ただ置くだけでは目立たないため、商品が魅力的に見える陳列が求められます。
最初は売れなかったものの、ポップをつけたり、商品を立体的に並べたりしたことで、売上が増えたという事例もあります。
ディスプレイに工夫をこらすことが成功のカギとなるでしょう。
委託販売のメリット
委託販売は、お店に作品を預けて販売してもらう方法です。
お店の力を借りられるため、以下のようなメリットがあります。
- 店舗が販売を代行してくれる
- 作家が接客する必要がなく、他の仕事や制作に集中できます。
- お店の集客力を活用できる
- 人気のあるお店なら、多くのお客様に作品を見てもらうチャンスが増えます。
- 店舗の信用を借りられる
- 大型店舗や有名ショップで販売できれば、作家としての信頼度もアップします。
委託販売を依頼したお店が人気店であれば、お客様が自然と作品を手に取る機会が増え、販売につながりやすくなります。
委託販売のデメリット
しかし、委託販売にはデメリットもあるため、事前に理解しておくことが大切です。
- 販売手数料がかかる
- 売上の20%~60%が手数料として引かれることが多く、利益が少なくなることもあります。
- 価格設定に制約がある
- お店によっては「○○円以上の商品のみ」というルールがあるため、自由に価格を決められない場合があります。
- 売れ残るリスクがある
- 作品が売れなかった場合、在庫をそのまま引き取る必要があり、無駄になることもあります。
例えば、ある作家さんが委託販売を始めたものの、手数料が高くて利益がほとんど出なかったというケースもあります。
事前に手数料や契約内容をしっかり確認し、納得できる条件の店舗を選ぶことが大切です。
ネット販売と組み合わせがおすすめ
ハンドメイド作品を販売するなら、レンタルボックスや委託販売だけでなくネット販売も併用するのがおすすめです。
ネット販売を組み合わせることで、販売のチャンスを広げ、売上アップにつなげられます。
特に、手間を減らしたい人や、手数料を抑えたい人にとっては、大きなメリットがあります。
ネット販売の方が手軽で続けやすい
ネット販売は、自分の都合に合わせて運営できるため、忙しい人でも続けやすいのが魅力です。
レンタルボックスや委託販売と違い、店舗に作品を持ち込む必要がなく、ネット上で完結します。
ネット販売の手軽さのポイント
- 24時間販売できる
- お店の営業時間に縛られない
- 在庫を管理しやすい
- 売れた分だけ追加すればOK
- 出品の手続きが簡単
- スマホやパソコンがあればすぐに販売可能
例えば、レンタルボックスでは作品を定期的に補充したり、ディスプレイを整えたりする手間がありますが、ネット販売なら一度出品すれば、追加の作業は最小限で済みます。
空いた時間を新しい作品づくりに充てることもできるため、効率よく販売を続けられます。
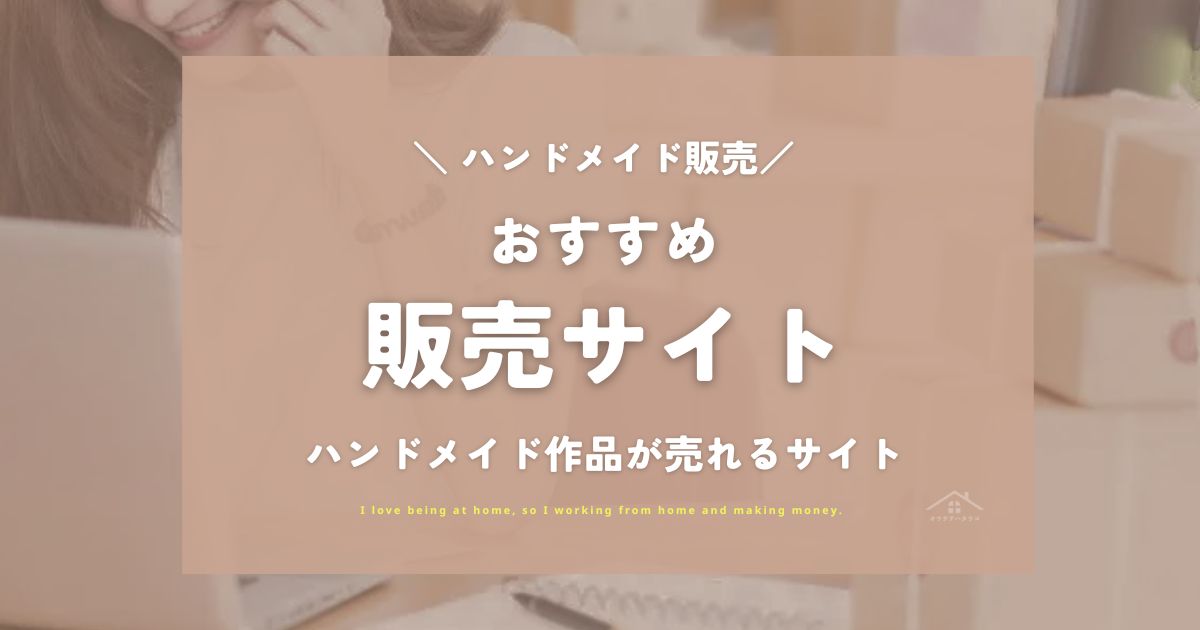
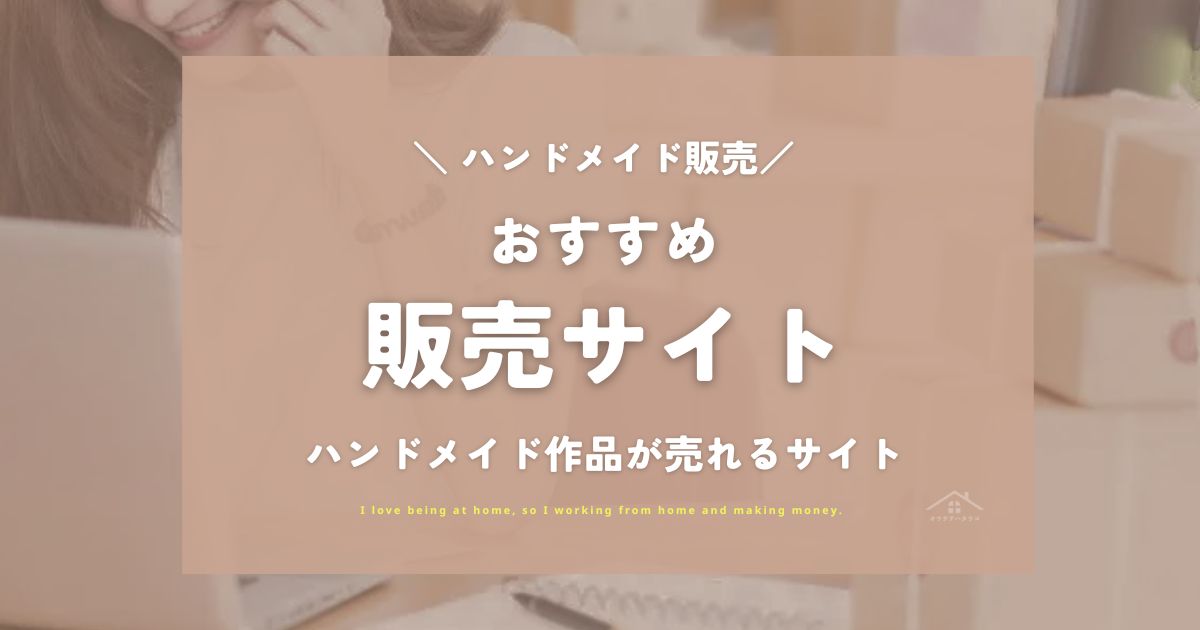
手数料が安く、多くの人に見てもらえる
レンタルボックスや委託販売では、出店料や販売手数料がかかります。
特に委託販売では売上の20~50%が手数料として引かれることもあります。
一方で、ネット販売なら比較的低い手数料で運営できるため、利益を確保しやすいのが特徴です。
ネット販売の手数料(例)
- minne:販売手数料 10.56%(決済手数料込み)
- Creema:販売手数料 5~12%(決済手数料は別途必要)
これに対し、レンタルボックスは月額数百円~数千円のスペース代、委託販売では販売手数料20%以上かかることが一般的です。
ネット販売のほうがコストを抑えられるため、売上を伸ばしやすくなります。
さらに、minneやCreemaなどのハンドメイドマーケットでは、全国の人が作品を見てくれるため、店舗に依存せず、多くのお客様に届けられるのも大きなメリットです。
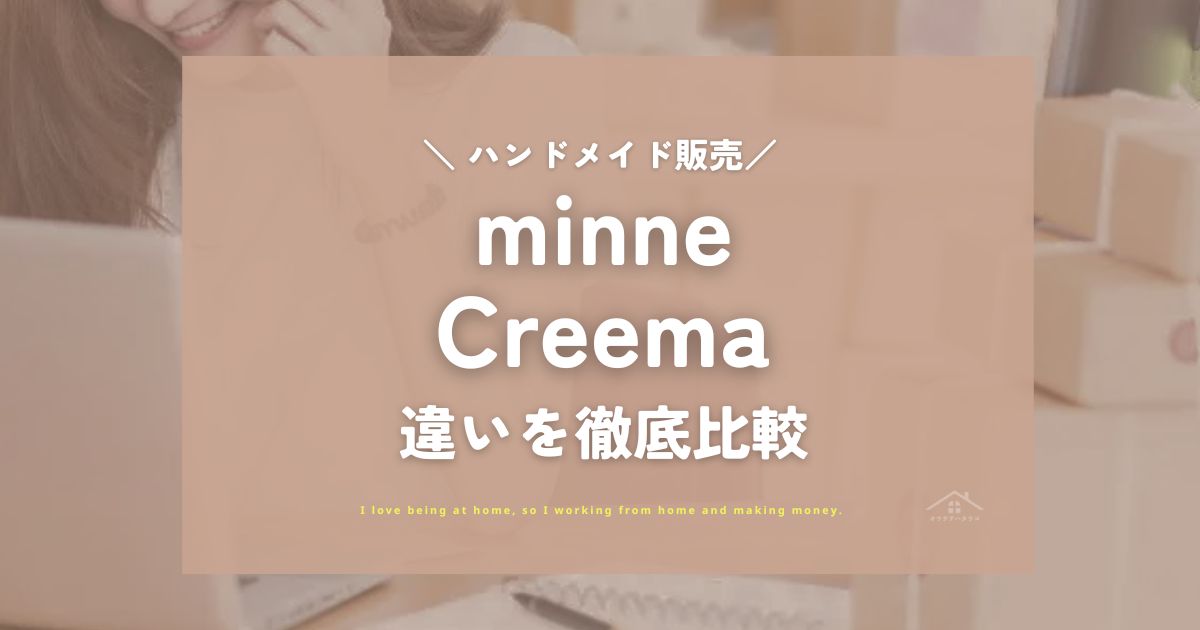
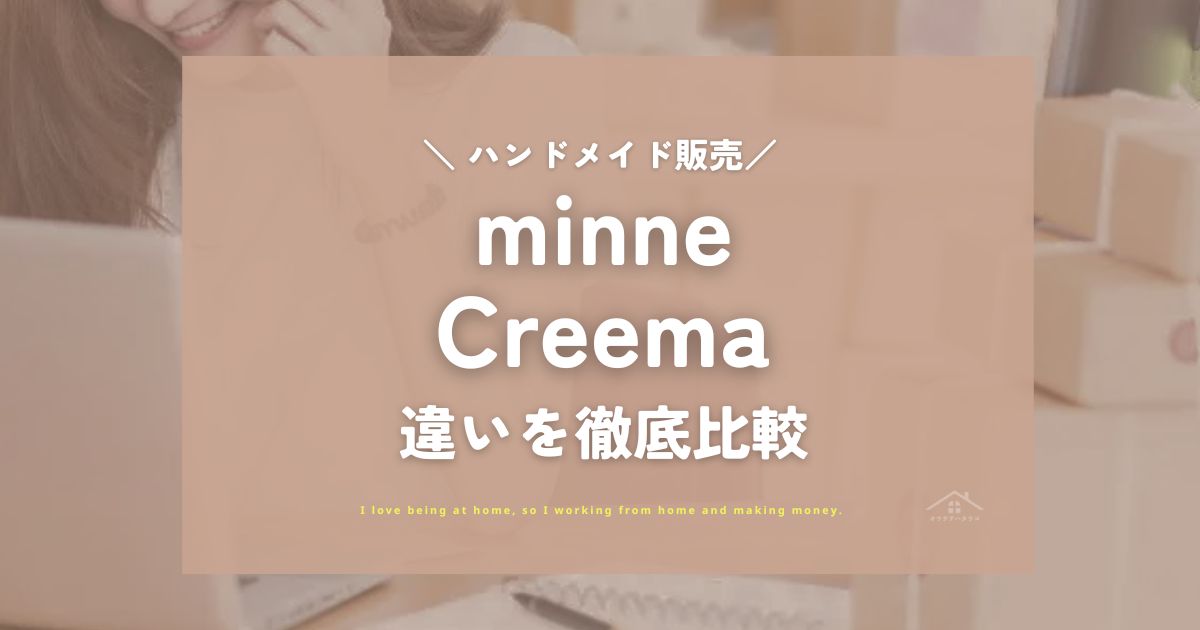
ネット販売×実店舗の活用例
ネット販売は便利ですが、実際に手に取ってもらえないため、「サイズ感がわかりにくい」「素材の質感が伝わらない」といったデメリットもあります。
そのため、レンタルボックスや委託販売を併用すると、より多くの人に作品を届けやすくなります。
- 実店舗で見てもらい、ネットで購入してもらう
- ネットで販売しつつ、委託店舗で試しに手に取れるようにする
- 店舗で売れ残った作品をネットで販売する
例えば、実店舗で「この作品、かわいいけど迷うな…」と思ったお客様が、後日ネットで購入することもあります。
そのため、ネット販売の名刺やネットショップのQRコードを、レンタルボックスや店舗に置いておくのも効果的です。
まとめ|自分に合った販売スタイルで売上アップを目指そう!
ハンドメイド作品を販売する方法には、レンタルボックスや委託販売、ネット販売などさまざまな選択肢があります。
それぞれに特徴があり、うまく組み合わせることで売上を伸ばせる可能性が高まります。
本記事では、レンタルボックスと委託販売の違い、売れるための工夫、そしてネット販売との併用のメリットを詳しく解説しました。
「どこで売るか?」だけでなく、「どう売るか?」も意識することで、売上は大きく変わります。
ぜひ本記事を参考に、自分に合った販売方法を見つけ、ハンドメイド作品を多くの人に届けてくださいね!