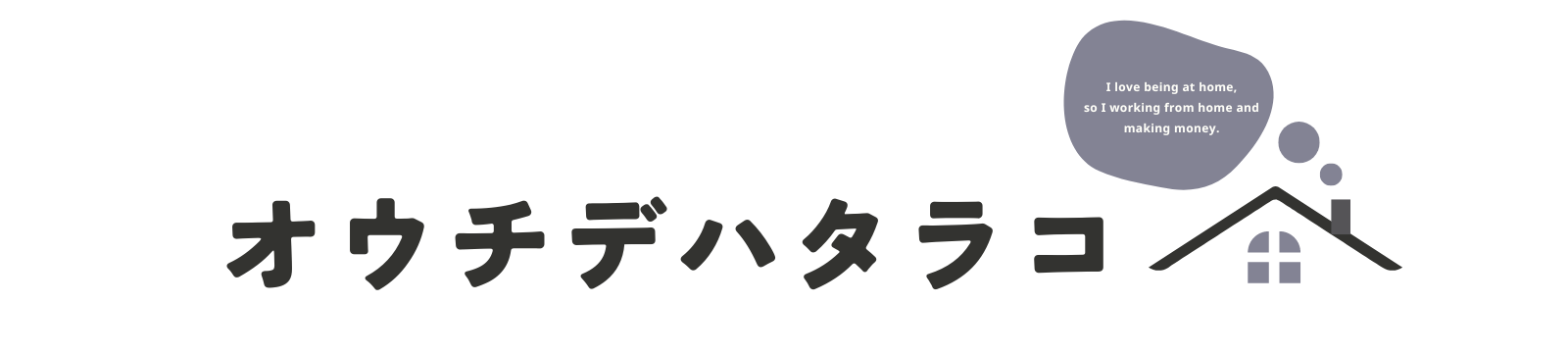Webデザインの用語って何があるのかな?
Webデザインを学び始めた初心者の方は、用語が多くて難しい、と悩むことが多いのではないでしょうか。
専門用語がわからないと、学習が進まず挫折しそうになりますよね。
この記事では、初心者向けにWebデザインの基本的な用語をわかりやすく一覧にまとめています。
この記事を読むことで、用語の意味を具体例とともに理解し、デザイン学習の土台をしっかり作ることができます。
Webデザインの世界をもっと楽しむために、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。




Webデザイン用語:初心者が知るべき基本用語とは?
Webデザインを学ぶ際には、基本的な用語を知ることがとても重要です。
その理由は、用語を理解することで、学習や作業がスムーズに進み、迷わずに取り組めるからです。
特に初心者の方は、専門的な言葉に慣れていないため、基礎から学ぶことで苦手意識を減らすことができます。
- 専門用語の意味を知ることで、他の人と会話や相談がしやすくなる。
- 本や動画で学ぶとき、理解が深まり学習効率が上がる。
- デザインのアイデアを形にする際、より的確に作業が進められる。
Webデザイン用語は最初は難しく感じるかもしれませんが、基礎を押さえておくことで確実にステップアップできます。
次に、具体的な用語について解説していきます。


Webサイトの種類
Webデザインを学ぶうえで、まず知っておくべきなのが「Webサイトの種類」です。
これを理解すると、作るサイトの目的に合わせて適切なデザインや機能を考えることができるようになります。
Webサイトにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。
ここでは、代表的な例をご紹介します。
- コーポレートサイト
- 企業の情報やサービス内容を紹介するためのサイトです。
- 「会社の沿革」や「事業内容」、「お問い合わせページ」などが含まれます。
- シンプルで信頼感のあるデザインが求められることが多いです。
- ECサイト(通販サイト)
- オンラインストア、ショッピングサイトなど、商品を購入できるサイトのことです。
- 例として、Amazonや楽天市場があります。
- 訪問者が簡単に商品を探せるように、商品カテゴリや検索機能が使いやすく作られています。
- プロモーションサイト
- 特定の商品やサービスを宣伝するためのWebサイトのことです。
- ブログサイト
- 個人や企業が情報を発信するためのサイトです。
- たとえば、料理レシピを紹介するブログや、旅行記を書いたブログが該当します。
- 文章や写真が中心で、訪問者が読みやすいレイアウトが重視されます。
- ポートフォリオサイト
- デザイナーやクリエイターが自分の作品を紹介するためのサイトです。
- デザインや写真が多く使われ、自分のセンスやスキルをアピールする場として使われます。
- LP(ランディングページ)
- 特定の目的を達成するために作られた1ページ完結のWebサイトです。
- 例えば、商品の購入を促したり、問い合わせを獲得したりと、訪問者に具体的なアクションを促す役割があります。
- LPの特徴を理解することで、より効果的なWebデザインを設計できるようになります。
具体例
- たとえば、ケーキ屋さんを始めるなら、店舗情報やメニューを載せた企業サイトを作るのがおすすめです。
- 一方、ケーキを販売したい場合は、ECサイトが適しています。
このように、サイトの種類によってデザインや必要な機能が変わるため、まずは目的を明確にすることが重要です。
Webサイトの種類を知っておくことで、どのようなデザインが必要かイメージしやすくなります。
次に学ぶ際の土台として、ぜひ押さえておきましょう。


Webページの構成の用語
Webデザインを学ぶとき、まずはWebサイト全体に関わる基本的な用語を理解することが大切です。
これらの用語を押さえておくことで、デザインだけでなく、サイトの構造や役割についてもイメージしやすくなります。
特に初心者の方にとっては、全体像を把握することがスムーズな学習の鍵になります。
Webサイト全体に関する主な用語
- トップページ
- Webサイトを開いたときに最初に表示されるページのことです。家でいう玄関のような役割を果たします。
- トップページには、サイトのメイン情報やメニュー(ナビゲーション)が配置されており、訪問者が次にどこに進むかを決めやすいように設計されています。
- ショッピングサイトでは「セール情報」や「人気商品」が目立つ場所に載せられています。
- ヘッダー
- Webサイトの一番上にある部分です。
- サイト名やロゴ、メニューなどが表示されており、どのページでも共通していることが多いです。
- ヘッダーがわかりやすいと、訪問者が迷わずにページを移動できます。
- たとえば、メニューに「ホーム」「商品一覧」「お問い合わせ」などが並んでいることがよくあります。
- フッター
- Webサイトの一番下にある部分を指します。
- 会社情報やプライバシーポリシー、連絡先などが表示されることが多いです。
- フッターは、訪問者が「もっと詳しく知りたい」と思ったときの頼りどころとなります
- 。例えば、企業サイトでは住所や電話番号が記載されていることが一般的です。
- ナビゲーション(メニュー)
- 訪問者がページを移動しやすくするために用意されたリンクの一覧です。
- 通常、ヘッダーやサイドバー、フッターに配置されています。
- たとえば、ECサイトなら「商品カテゴリ」「カートを見る」「会員登録」などのリンクが並んでいます。
- ナビゲーションが整理されていると、訪問者が目的の情報にたどり着きやすくなります。
- ハンバーガーメニュー
- スマートフォンやタブレットなどの画面でよく使われる、三本線のアイコンをタップするとメニューが表示される仕組みのことです。
- このアイコンがハンバーガーの形に似ていることからそう呼ばれています。
- サイドバー
- ページの横に配置される補助的な情報のスペースです。
- ブログなら「人気記事」「最新記事」「カテゴリー一覧」などがよく使われます。
- サイドバーがあることで、訪問者が他のページも見てみようと思うきっかけを作ることができます。
- パンくずリスト
- Webサイトで今いるページの位置を階層的に表示する案内のことです。
- ページ上部に「ホーム > カテゴリ > サブカテゴリ > 現在のページ」のような形で表示されます。
- コンテンツ
- Webサイトに掲載されている文章や画像、動画などの情報をまとめて「コンテンツ」と呼びます。
- たとえば、ブログなら記事の本文や写真がコンテンツにあたります。
- Webサイトの価値は、このコンテンツの質によって決まると言っても過言ではありません。
- FV(ファーストビュー)
- Webサイトを開いたときに最初に表示される画面のことを指します。
- サイトの第一印象を決める重要な部分。
具体例
たとえば、
- 学校のWebサイトを作る場合、トップページには「学校の特徴」や「入学案内」を、ヘッダーには「ホーム」「学校紹介」「アクセス」などのメニューを配置します。
- そして、フッターには住所や連絡先、ナビゲーションに「校長のメッセージ」や「行事予定表」を載せるといった流れになります。
これによって、訪問者は欲しい情報を簡単に見つけられるようになります。
Webサイト全体の用語を理解することで、どの部分が何の役割を果たしているかがわかり、効率的にデザインを学べます。
初心者の方は、この基礎をしっかり押さえることが大切です。
レイアウト用語
レイアウトに関する用語を見ていきましょう。
レイアウト
レイアウトとは、Webページに文字や画像をどのように配置するかを指します。
訪問者が読みやすいように工夫することが大切です。
例えば、見出しを大きくして、重要な情報を目立たせるデザインが一般的です。
カラム・カラムレイアウト
Webサイトや印刷物のデザインにおいて、内容を縦に分けた区切りのことを指します。
簡単に言うと、新聞や雑誌の紙面で見る「縦に分けられた文章の列」をイメージしてください。
Webサイトでも、この考え方を使ってページを整理し、見やすくしています。
ページを複数の列(カラム)に分けて、情報を整理しやすくするために使われます。
主な種類
- 1カラム:1列構成。
- 2カラム:2列、左右に分けた構成。
- 3カラム:3列構成。
グリッドレイアウト
ページを縦横の格子状(グリッド)に分割して要素を配置するデザイン方法のことです。
要素が揃って配置され、スッキリした印象を与えます。
メイソンリーレイアウト
高さが異なる要素を隙間なく配置するデザイン手法のことです。
レンガを積み上げたような見た目で、Pinterestやギャラリーサイトでよく使われるデザイン。
メイソンリーレイアウトは、画像やコンテンツが多いサイトに最適な配置方法です。
Webデザイン用語
- 余白(ホワイトスペース)
- 余白とは、文字や画像の周りにある空間のことです。
- 余白が適切に取られていると、ページが見やすくなります。
- たとえば、ぎっしり詰まった文章よりも、適度に空間がある方が読みやすく感じます。
- マージン
- Webデザインや印刷物で、要素と要素の間に取る外側の余白のことを指します。
- 文字や画像、ボックスなどの要素同士の「間隔」を調整するために使われます。
- パディング
- Webデザインや印刷物で、要素の中の内容とその枠との間に取る内側の余白のことを指します。
- 文字や画像などのコンテンツが枠にくっつかないように調整するために使われます。
- フォント
- 文字のデザインや書体のことを指します。
- 文字の形や太さ、大きさなど、見た目を決める要素です。
- カーニング
- 文字と文字の間隔を調整することを指します。
- 特に、文字の見た目が不自然に詰まりすぎたり離れすぎたりしている部分を、読みやすく見た目の良い状態に整える技術です。
- Webデザインや印刷物のデザインで重要なポイントとなり、文章の美しさやプロらしい仕上がりに大きな影響を与えます。
- h1(エイチワン)
- Webページ内で一番大事な見出しを表すHTMLタグのことです。
- ページのタイトルやメインテーマを示す役割があります。
- サムネイル
- 画像や動画の内容を小さく表示した見本画像のことを指します。
- クリックすると元の大きな画像や動画が表示される仕組みが多いです。
- 配色(カラーリング)
- 配色とは、Webサイトで使用する色の組み合わせのことを指します。
- どんな色を選ぶかによって、サイトの印象が大きく変わります。
- たとえば、銀行のサイトでは信頼感を与える青系の色がよく使われます。
- 一方、子ども向けのおもちゃのサイトでは、明るい黄色や赤が多いです。
- トンマナ
- 「トーン&マナー」の略で、デザインや文章の「全体的な雰囲気」や「統一感」を指す言葉です。
- あしらい
- デザインやレイアウトを作るときに、主役を引き立てるために配置する装飾や補助的な要素のことを指します。
- アール
- デザインで使われる角の丸み(曲線)のことを指します。
- 四角形の角を滑らかな曲線にすることで、柔らかい印象や親しみやすさを与えるデザインができます。
- ボタンや枠線、カードデザインなどによく使われます。
- コントラスト
- 明度や色相の差のこと。色や明るさの差を指し、要素を際立たせるためのデザイン手法です。
- ビットマップデータ
- 画像を小さな点(ピクセル)の集まりで表現する形式のことです。
- それぞれのピクセルに色が割り当てられており、これが集まって1つの画像を構成します。
- 写真や複雑なグラフィックでよく使われます。
- Photoshopのデータ方式。
- ベクターデータ
- 図形や線、文字などを数式や座標で表現するデータ形式のことです。
- 点と点を結ぶ線や図形の情報を数値で記録しているため、拡大や縮小をしても画質が劣化しないのが特徴。
- イラストやロゴなど、シンプルなデザインに最適。
- Illustratorのデータ方式。
- デザインカンプ
- Webサイトや印刷物の完成イメージを示すデザイン見本のことです。
- 本番制作に入る前に、レイアウトや配色、デザインの全体像を確認するために作られます。
フラットデザイン
影や立体感を使わず、シンプルで平面的にデザインされたスタイルのことです。
余計な装飾を排除し、色や形でわかりやすく情報を伝えるのが特徴です。
マテリアルデザイン
マテリアルデザインとは、Googleが提唱したデザイン手法で、フラットデザインのシンプルさを取り入れながら、影や動きを使って立体感や奥行きを表現するのが特徴です。
レスポンシブデザイン
レスポンシブデザインとは、スマートフォンやタブレット、パソコンなど、異なる画面サイズに対応するWebデザインの手法です。
1つのHTMLファイルで画面幅に応じてデザインを変化させ、どのデバイスでも見やすく使いやすいページを提供します。
UI(ユーザーインターフェース)
UIとは、User Interface(ユーザーインターフェース)の略称。
Webサイトやアプリなどで、ユーザーが操作する部分や見える部分のことです。
たとえば、ボタンやメニュー、入力フォーム、画像などがUIにあたります。
つまり、訪問者や利用者が実際に触れたり、目で見たりするデザインの部分を指します。
UX(ユーザーエクスペリエンス)
UXとは、User Experience(ユーザーエクスペリエンス)の略称。
Webサイトやアプリなどを使ったときに得られる「体験」や「満足感」のことを指します。
使いやすさ、分かりやすさ、デザインの美しさだけでなく、「使って楽しかった!」「また利用したい!」と感じてもらうことが目標です。
Webサイトのギミックの用語
Webサイトのギミックの用語を見ていきましょう。
ホバー
ホバーとは、Webサイトでマウスカーソルを特定の要素(ボタンや画像など)に重ねたときの状態のことです。
ホバー時に、色が変わったり、動きが追加されたりする仕組みがよく使われます。
カルーセル
カルーセルとは、画像や情報をスライドショーのように横に並べて表示し、順番に切り替わる仕組みのことです。
主にWebサイトのトップページや商品紹介の部分で使われます。
アコーディオン
アコーディオンとは、クリックやタップで隠れている内容を開閉できる仕組みのことです。
Webサイトで、FAQ(よくある質問)やメニューなどに使われることが多いです。
モーダルウィンドウ
モーダルウィンドウとは、Webサイト上で画面の一部に重ねて表示される小さなウィンドウのことです。
背景が薄暗くなることが多く、ユーザーの注意をウィンドウ内の内容に集中させるために使われます。
Webデザイン用語を覚えることで得られるメリット
Webデザインに関する用語を覚えることで、次のようなメリットがあります。
- 作業がスムーズになる
- 専門用語の意味を理解すると、指示や解説をすぐに理解できます。
- デザインの質が向上する
- 用語を活かした工夫を取り入れることで、見栄えや使いやすさが向上します。
- 学習が楽しくなる
- 意味を知ることで、デザインがどんどん楽しくなり、自分のスキルに自信が持てます。
Webデザインに関する基本的な用語を知ることで、学びの幅が広がります。
最初は覚えるのが大変かもしれませんが、一つひとつ具体例とともに理解することで、デザインの楽しさを感じられるようになりますよ!
Webデザイン用語:まとめ
Webデザインの学習を始めたばかりの初心者にとって、専門用語や基礎知識を理解するのはハードルが高いと感じるかもしれません。
しかし、基本用語を正しく理解することで、スムーズに学習を進められるだけでなく、デザイン全体のイメージもつかみやすくなります。
この記事では、Webデザイン初心者が押さえるべき用語をわかりやすく解説しました。
少しずつ経験を積むことで、自分の中にデザインの軸ができ、魅力的なWebサイトを作れるようになります。
初心者の方でも、一歩一歩着実に進んでいきましょう!